ガイドライン
疾患
・ネフローゼ症候群( Nephrotic syndrome)は、腎糸球体係蹄障害による蛋白透過性亢進に基づく大量の尿蛋白漏出と,これに伴う低蛋白(低アルブミン)血症を特徴とする症候群である.
・ネフローゼ症候群では腎機能障害(慢性腎臓病および急性腎障害)の他,蛋白喪失に伴う合併
症として浮腫,脂質異常症,血液凝固異常(血栓傾向),内分泌異常,免疫不全,易感染性などさまざまな病態を合併する.
・病理学的には糸球体基底膜の透過の亢進を一次的異常として認める。時に脂質異常症も合併する。
・ネフローゼ症候群は、原発性糸球体疾患に起因する「一次性」と、続発性糸球体疾患による「二次性」に分類される。
原因疾患
一次性ネフローゼ症候群
二次性ネフローゼ症候群の原因疾患
ネフローゼ症候群の症状
・浮腫(眼瞼や下肢)、強度の全身倦怠感、皮膚の蒼白化や無気力、食欲不振、腹水・胸水・血尿、など。
・主に、アルブミンなどの血中タンパクが排泄されるため、血中タンパクが減少し、血漿膠質浸透圧が低下する。このため、全身に浮腫を形成する傾向が現れる。
・また、尿中タンパクが増大するため、尿の浸透圧が増大し、尿細管における水の再吸収が抑制され、一過性に利尿傾向となる。
・この遺失タンパク分を肝臓が補完しようとするため、肝臓がアルブミンの合成を開始するが、同時にLDLのようなコレステロール運搬タンパクも合成してしまうため、高頻度に脂質異常症の状態をみることがある。
・長期の利尿期間を経て、腎臓の病態が改善されず、高度に腎不全の状態を呈し始める時期には、乏尿となる。
検査値
・蛋白尿≧3.5 g/日(随時尿において尿蛋白/クレアチニン比が 3.5 g/gCr 以上の場合もこれに準ずる)、血清アルブミン値≦3.0 g/dL (血清総蛋白量 ≦6.0 g/dL も参考)が必須項目で、浮腫、脂質異常症(高 LDL コレステロール血症)は参考所見。
(さんごのろくさんネフローゼ:3.5、6、3)
・脂質異常症(高LDLコレステロール血症)
ネフローゼでは大量のタンパク尿によりアルブミンが失われ、血液中のアルブミン濃度が低下します。アルブミンが低下すると、血漿膠質浸透圧が下がり、体はそれを補おうとして肝臓でアルブミンを増産します。しかし肝臓は同時にリポ蛋白(VLDL, LDLなど)の産生も増やすため、血中コレステロールや中性脂肪が上昇します。
成人ネフローゼ症候群の診断基準 (ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020)
1 蛋白尿:3.5 g/日以上が持続する.
(随時尿において尿蛋白/クレアチニン比が 3.5 g/gCr 以上の場合もこれに準ずる)
2 低アルブミン血症:血清アルブミン値 3.0 g/dL 以下.
血清総蛋白量 6.0 g/dL 以下も参考になる.
3 浮腫
4 脂質異常症(高 LDL コレステロール血症).
注:
1)上記の尿蛋白量,低アルブミン血症(低蛋白血症)の両所見を認めることが本症候群の診断の必須条件である.
2)浮腫は本症候群の必須条件ではないが,重要な所見である.
3)脂質異常症は本症候群の必須条件ではない.
4)卵円形脂肪体は本症候群の診断の参考となる.
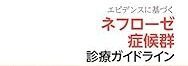

コメント